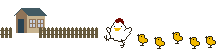
第59号 TVゲーム 子ども編
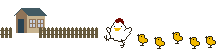
私は子どもたちの「何して遊ぶ?」という言葉が好きだ。
遊びが始まる前のあのヒマな時間。
ぶらぶらしているのもつまらないので、何かしようかという気になる。
そして、口から出てくる言葉。
「ねえ、何して遊ぶ?」
それから、相談が始まる。
幼稚園のころからそうだが、小4になった今でも同じである。
小4になってからは、オセロやチェスやトランプなどのゲームが増えたが、
3年生頃までは、いやというほど「ごっこ遊び」をしたものだ。
ごっこ遊びの相談がこれまた楽しい。
まず、何ごっこにするか決める。
「家族ごっこ」にきめたら、次は状況を設定する。
「お母さんは死んじゃったのね」(殺すなってば!)
「お姉さんと妹と赤ちゃんで暮らしているのね。」
てな具合だ。
学校ごっこだって、病院ごっこ(耳鼻科、歯科、内科、入院編などいろいろある)だって、
そうやって状況設定してから、役を決め、ストーリーを作って遊んでいく。
たまに演芸会みたいなことをする。
そのときは、どんな芸を披露するか話し合い、練習し、
芸がしあがると私は客にさせられる。
これはかなり笑える。
私はこんな子どもたちの遊びをみていて、その豊かさにいつも感心する。
![]()
![]()
![]()
私は子どもが生まれる前、ファミコンに熱中した時期がある。
朝、目を覚ました夫に「何やってんの?」と声をかけられ、
一晩中ファミコンをやっていたことに気がついた・・・なんてことさえあったほどだ。
ドラクエには相当ハマッた。
テトリスやクラックスなどの積み木系の熟達ぶりは相当なものだった。
自分で熱中していながら、こういうのもなんだが、
妊娠したとき、自分の子どもには、絶対ファミコンはやらせたくないと思った。
ほとんど苦痛も感じず、5時間も6時間もし続けることができるなんて、そもそもおかしい。
目に悪いとか、体に悪いとか以上に、頭がおかしくなりそうだ。
そのうち、ファミコンは夫が友人に譲ってしまった。
ちょうど、娘が通った幼稚園は、「TVはあまり見せないようにしましょう」という方針だったので
進んでTVゲームを子どもに与えるような親がいなかった。
だから、友達の家へ行ってTVゲームをしてくるということもなかったし、
うちに来た子が「TVゲームがないの?」と不平をいうこともなかった。
![]()
![]()
![]()
長女が小学校にあがってしばらくしたとき、友達がゲームボーイをもって遊びにきた。
その子は、ずっと一人でゲームボーイをやっていた。
長女は何度も「やらせて」とせがんだが、友達は貸してくれず、娘はストレスに耐えかねる様子だった。
せっかく友達と二人でいるのに、黙って片方の子どもがゲームをしているのを娘は見ているだけ・・・
こんな遊び方で貴重な子ども時代を棒に振ってしまうなんて、なんとももったいないと、私は思った。
それで、その子が帰るとき、私は子どもたちに宣言した。
「これから、うちは”ゲームボーイ禁止”です。
うちに遊びにくるときは、ゲームボーイを持ってきてはいけません。
○○ちゃんだけではなく、どの子もです。
ゲームボーイは一人でもできます。
一人でできる遊びは自分の家でやってください。
友達がいるときは、友達と遊びましょう。」
子どもたちは納得した。
その友達は今でもよく遊びにくるが、二度とゲームボーイをもってこない。
もちろん、それ以降うちにゲームボーイを持ってくる子はいない。
![]()
長女が1年生のころ、親子で友達の家へ誘われ私も一緒に遊びに行った。
そこにはうちの子以外に何人か遊びにきていた。
が、私たちがおじゃました3時間の間、子どもたちはずっとTVゲームをしていた。
1ゲームずつ順番にやっているとか言っていたが、
一人の子がゲームをしている間、他の子たちは一緒にそのTV画面を黙ってみているのだ。
お菓子をつまみに立ち歩く子もたまにいるが、子どもの動きはそれくらいで、
あとはずっと同じ場所でじっと画面を見つづけている。
それだけで時間が過ぎ去っていくのだ。
子どもが遊べば必ず出てくるはずの相談も役決めも準備も何もない。
普通、低学年の子どもが3時間もの間、
じっと同じ場所に座ったきりで同じ格好をしていられるものだろうか。
指先と大脳の一部は使っているかもしれないが、豊かな人間関係はゼロに近い。
TVゲームは恐ろしいと痛く思った。
![]()
![]()
![]()
某兄弟が遊びにきたときのこと。
先方のお母さんもきていたので、私たちは大人同士でお茶していると、
隣の部屋から「うんこ大会」とかいう言葉が聞こえてきた。
そのうち、下の子たちが招待状を持ってきた。
招待状には、うんこの絵が描いてあった。
友人宛てのも私宛のもどちらも
自分のうんこの絵のうまさを自負するかのような見事な描きっぷりだった。
下の子たちは、上の子に言われたらしく
「うんこ大会をします。準備ができたら来てください」
と言って去っていった。
準備ができると、また、下の子たちが呼びにきた。
呼ばれた部屋へ行ってみると、ドアにはうんこの絵がたくさん貼られていた。
そして、いきなり友人のご長男さんのうんこの歌がはじまり、
うちの長女は、チンドン屋さん風に古い鍋を調子よく叩いた。
そして、下の子たちがそれに合わせて、
ものの影からぴょこりぴょこりと出たりひっこんだりしながら
「うんこ踊り」なるものを披露してくれた。こんな接待が終わると、
「では、お母さんたちにうんこの絵を描いてもらいます」
と言って、私たちは紙と鉛筆を渡されてしまった。
「まいったな〜〜」と思いつつも、子どもの手前下手なうんこを描くわけにはいかない。
私はソフトクリーム式のうんこを描いた。
友人は、いかにもトイレで見かける普通の10cmくらいの棒状のうんこを描いた。
私は内心「なかなかやるな」と感心したが、口には出さなかった。
![]()
![]()
![]()
子どもたちのお楽しみのひとつに「肝試し大会」がある。
うちは、結構気軽によその子が泊まりにくるのをOKするので、
そんな晩は必ず布団に入る前に「肝試し大会」が開催される。
うちには、夜になると怖くて歩けなくなる長い廊下がある。
娘は普段歩けないその廊下を友達が来た晩だけは歩きたくなるらしい。
もちろん、始まる前には話し合いがある。
だから、友達によってルールは異なるが、
お札をもって、最初は二人組みで、次は一人で廊下を歩き、
随所に置かれた証拠のスタンプを押してくるという流れは変わらない。
ちなみに、「お札」というのは、紙に「おふだ」と自分で書いた、ただの紙切れである。
が、それを持つとどうやら勇気百倍になるらしい。
終わると、みんな「ああ、面白かった」と満足して布団に入る。
TVゲームよりずっと楽しい遊びがあることをこの子たちは知っている。
![]()
普段ゲームで遊んでいる子がうちに遊びにくると、
ゲームがないので、はじめはヒマそうにしているが、
そのうち、なにかしら遊びはじめる。
ないならないで子どもっていうのは、いろんなことを考えつくのだ。
大事な子ども時代、TVゲームよりもっと面白いことがあることを多くの子どもたちに体験してほしい。
「うんこ大会」や「肝試し大会」を陽気に計画するような愉快な子どもになってほしい。
![]()